◆設定◆
・齋藤学PF
職業:金型工場の営業マン(勤続22 年)
会社:株式会社ストレートライン
年齢:45 歳(バツイチ)
趣味:読書/ 映画鑑賞
楽しみ:取引先の女性社員との打ち合わせ
・三ツ島かおりPF
職業:アダルトグッズメーカー勤務(勤続3年)
会社:Oto Inc.
年齢:23 歳(独身)
趣味:ナンパ
楽しみ:複数プレイ
◆ストーリー
企画会議のためOto Inc. に出向いた日に、まさかの出来事が起きた。
その日は、勤務中はいたって真面目な神崎おとはと、たくさんの資料やサンプルを前に完全な仕事モードで打ち合わせをしていた。
「新商品の製造工程については、これで問題ないですね。」
根を詰めて話して少し疲れていた私は、一息ついて頷いた。
「そうだね。」
早くプライベートで神崎さんと会いたいなぁ、と内心指を咥えながらも、私は真面目な表情を崩さなかった。
「では引き続き、商品ビジュアルについてもお話させていただければと思います。齋藤さん、この商品のパッケージデザインを担当している弊社の社員を紹介してもよろしいでしょうか?」
「それは、もちろん。」
断る理由などないので、私は当たり前に許諾した。
「少しお待ちください。」
そう言って、神崎さんは一旦会議室を出ていった。私は一服しようとタバコを咥えた。ゴソゴソと胸ポケットからライターを取り出して火をつけたが、「終日禁煙」の張り紙が目に入り、ライターの火を消した。
その時、神崎さんが一人の女性社員を連れて戻ってきた。部屋に入ってきたその女性を見た瞬間、私の全身に鳥肌が立ち、タバコが口からポロっと落ちた。
私の動揺をよそに、神崎さんは淡々と女性を紹介した。
「こちら、弊社のパッケージデザインを担当している三ツ島です。」
「はじめまして。三ツ島かおりと申します。どうぞよろしくお願いいたします。」
こんな偶然あるのだろうか。見覚えのある壇〇似の色っぽいオフィスレディ。彼女はまさしく、あの日DVDショップで逆ナンパされた・・・!
精一杯平静を装って、私は乾いた笑顔を向けて挨拶をした。
「齋藤学と申します。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします」
彼女の方も会釈して言った。
「いつもお世話になっております。」
「え、お、お世話?」
私は神崎さんの表情を横目で確認した。冷や汗をかく私を不思議そうに見つめている。
あの日はたっぷり「お世話」してもらったが…、そのことを言ってるワケじゃない。
三ツ島かおりは顔色ひとつ変えず、にっこりと笑みを携えていた。
「神崎から色々とお話はお伺いしております。」
「ふぇっ! そ、それはどんな話を…?!」
まさか枕営業のことを話したのか? もしや、とびっこデートのことまで?
意味深にも聞こえるその言葉に、私は変な声を挙げてしまった。
「齋藤さんはいつも仕事熱心で気が利く大人の男性だと。でも、お会いしたら思っていたよりも可愛らしい人なんですね。」
三ツ島かおりは鈴の音のような声でクスリと笑った。冷や汗ダクダクの私とは対照的に、神崎さんは部下の失礼な言動に対して少々お冠の様だった。
「三ツ島、大切なお取引先の方に失礼でしょう?」
「すいません。」
三ツ島かおりが悪びれもせず、すました笑顔で頭を下げる。私はどうにか気持ちを立て直し、大人の余裕をもって応対した。
「いえいえ、神崎さん。構いませんよ。こういうフレンドリーさは若さの特権ですからね。はっはっはっ」
「教育不足で本当に申し訳ありません。」
「本当に、気にしてませんから。それに、僕は神崎さんみたいな綺麗な女性からそんな評価をいただけるほどの男ではありませんよ。」
「何をおっしゃるんですか! 私は斎藤さんの真摯な姿勢を尊敬しております。もっと自信を持っていいですよ。」
何だか褒め合う状況になってしまっていることに気づいて、お互いにハッと顔を見合わせて思わず照れてしまった。どう考えても不自然な空気の中、三ツ島かおりは意に介さぬ感じで、その中へと食い込んでくる。
「私もそう思いますよ。斎藤さんは、きっと素敵な男性なんだろうなぁって。初めてでも分かります。」
「え。あ、ありがとうございます。」
「初めて会った気がしないくらい。ふふっ。」
さっきから三ツ島かおりの天真爛漫さが、ボディーブローのように効いてくる。三人の間に流れている微妙な空気、もしかして神崎さんに勘づかれてしまうのではないか。わけわかんなくなって、我慢汁まで出てきてしまいそうだ。体の回路が明らかにおかしい。
しかしここで、神崎さんが上司として再度、三ツ島かおりを叱咤した。
「三ツ島。いい加減にしなさい。余りにも馴れ馴れしいわよ!」
「すいません。では、私はそろそろ失礼致しますね。この後も二人っきりでごゆっくりお打ち合わせをなさってください。」
「三ツ島!!」
神崎さんの強い口調に、三ツ島かおりは肩を竦めて去っていく。もちろん、反省の色は全く見えなかった。
後日、神崎さんと落ち合うことになった。いつもの枕営業だ。だが、ここでも思わぬハプニングが勃発してしまった。
「齋藤さん、先日のご無礼、大変申し訳ありませんでした…」
三ツ島かおりの馴れ馴れしい態度のことを、上司として殊勝に謝ってくる神崎さん。今日は珍しくワンピース姿で、ゆったりと開かれた胸元の谷間が悩ましい。
三ツ島かおりのことは、元を正せば自分に原因があるので、何も責めることはできない。
「いえいえ、気にしないでください。こちらこそ、不自然だったのではないかと思ってヒヤヒヤしてしまいました。」
「あの子、すごく勘がいいので、私の斎藤さんへの評価から、何か察していたのだと思います。」
「いや。確かに、もの凄く焦ったけど、あんな風に他の女の子にも言ってくれていたのは、正直ちょっと嬉しかったよ。」
偶然とはいえ、三ツ島かおりとも関係を持ってしまっている以上、下手なことは絶対に言えない。できれば、彼女についての話題は早々に終わりにしたかったのだが、仕事熱心で部下想いな一面のある神崎さんはフォローを続けた。
「三ツ島は少し気まぐれなところもあるのですが、普段なら初対面の相手には丁寧な対応をする子なんです。なので、あんな風になるなんて、ちょっと私も驚いてしまって…」
神崎さんがチラッと私を見る。
「そうなんですね。いやぁ、どうしてなんだろうなぁ。」
私はこのままトボけて話を流そうとしたのだが、そうは問屋が卸さない。神崎さんはふっと真顔になり、問い質すかのような口調で私に尋ねた。
「齋藤さん、三ツ島と以前どこかで会われましたか?」
なんという鋭い質問だろう。私はドキドキと早鐘を打つ心臓音が聞こえないよう、わざと声を張り上げて、頬を引き攣らせながら笑った。
「も、も、もちろん初めてだよ。君が連れてきて紹介してくれたんじゃないか。」
「実は、あのあと三ツ島から聞いたんです。あの子が逆ナンパをたまにしていて、ちょっと前に逆ナンパした相手が齋藤さんだったって告白されました。」
がっくりと肩が落ち、目の前が真っ暗になった。
バレてしまった。というか、すでにバレていた。なんで口止めしておかなかったんだろう?
「最初は信じられなかったけど、アソコのホクロとか、イキそうな時の声の上げ方とか、知ってて。」
神崎さんも少し照れながら言ったが、私は顔から火が出そうだった。第二の青春が終わったと、胸の内が絶望に染まっていったが、ここまできたら仕方がない。
私は顔を上げて神崎さんをまっすぐ見つめた。黒目がちの綺麗な彼女の瞳もまた、まっすぐに私を捉えている。私は素直に頭を下げ、誠心誠意の気持ちを持って謝罪をした。
「事実です。つい出来心で…。初めての経験で嬉しくなってしまって。本当に申し訳ありません。」
「謝ることはありませんけど…、本音で言えば、少しショックでした。」
「す、す、すいません!」
神崎さんは本当にちょっと悲しそうな顔をしていたが、私が必死で謝る様子に、クスリと笑って「怒ってませんよ」と優しい言葉を掛けてくれた。
ああ、まるで女神のような女性だと、改めて彼女の魅力を痛感する。しかし、次に神崎さんの口にしたセリフは、これまた想定外のものであった。
「それで、三ツ島との相性はいかがでしたか?」
「あ、相性?? それって体のってこと?」
「そうですよ。私には聞く権利があると思うんだけどなぁ。」
神崎さんは、ねだるような表情で私の股間をさすった。
「どうだったの?」
「え、えーと…、悪くはなかったけど、やっぱり僕には神崎さんが一番だよ!」
胸を張ってそう豪語した、その瞬間。特徴的な笑い声が背中から聞こえてきた。思わず振り向くと、そこにはニヤニヤとした笑みを口元に浮かべた三ツ島かおりが立っていた。
「お邪魔しま~す。齋藤さん、神崎先輩こんばんは!」
三ツ島かおりも普段着で、ニット地のタンクトップに黒いタイトパンツ。ヘソ出しで、豊満な体のラインがくっきりと出ている。
とんでもないゲストの登場に、私は驚いて今日一番の大声をあげた。しかし、神崎さんの方は平然としている。これはいったいどういうことなのだろうか。
「実はあの後、三ツ島と二人で齋藤さんについて話し合ったんです。それで、二人の共有財産にしちゃおうってことになって。」
神崎さんは悪戯っぽい笑みを浮かべて、楽しそうにそう言った。なるほど、もうすでに仕組まれていたというわけだ。三ツ島かおりも神崎さんの後ろに立って笑っている。
妖艶な美女二人に結託されてしまえば、ハッキリ言って男はもうお手上げだ。
「うふふ、せっかくなんで、私も仲間に入れてくださいねぇ。」
三ツ島かおりは愉快そうに笑い、私の隣の席に座って、するっと腕を絡めてきた。タンクトップの裾から横乳が覗く。まさか、ノーブラ??
背中がゾクゾクとする。ちょっとだけ、神崎さんの視線が痛い。
「そんな合意がなされていたんですね。それはもう、私は従わざるえない立場でございます…」
「ございますって。齋藤さんってば、やっぱり可愛い。今回は逆ナンの時以上にイジメちゃいますよ」
そう言って、三ツ島かおりはハリのある胸を押し付ける。
「もう、その話はしないで。嫉妬しちゃうわ。私も今日はいつも以上にイジメちゃいますからねっ!」
神崎さんも負けじと体を寄せ、柔らかな胸をギュッと押し当てて抱きついてきた。
「ふ、二人とも、落ち着いて…」
一番落ち着きをなくしているのは私の股間だったが、自分に言い聞かせるように二人をなだめた。
「齋藤さぁん」
二人揃って、私を挟み込むように甘えてくる。
目の前には、はち切れんばかりのおっぱいが並んでいる。
二人の美女が、それぞれ瞳を潤ませて誘ってくる。
「ね〜、今日はぁ、」と三ツ島かおりが甘い声を出せば、
「オモチャいっぱい買ってくださいね。」と神崎さんが艶っぽく囁く。
「それで、い〜っぱい遊びましょ❤︎」
「楽しみですね。」
「は…、はぁい。よろひくお願いひまぁす。」
私が降参して情けない声を上げげると、二人は嬉々として新しい商品のセールスを始めた。
「さっそくホテルでご覧くださいね。」
「私からは定期購買のご提案もさせていただきま〜す♪」
「て、て、て、定期購買?!」
「そ。忘れないように、毎月お楽しみをお届けするの。」
「ずっと一緒ってコトですよ。」
神崎さんが耳元で囁く。もう脳ミソまでとろけてしまったようだ。
「…そういうの大好きです! 今すぐにでも、サインさせていただきます!」
「焦らなくても、私たちもオモチャも、逃げたりしませんよ?」

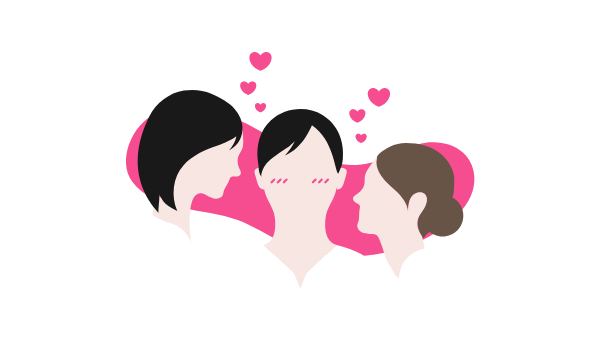



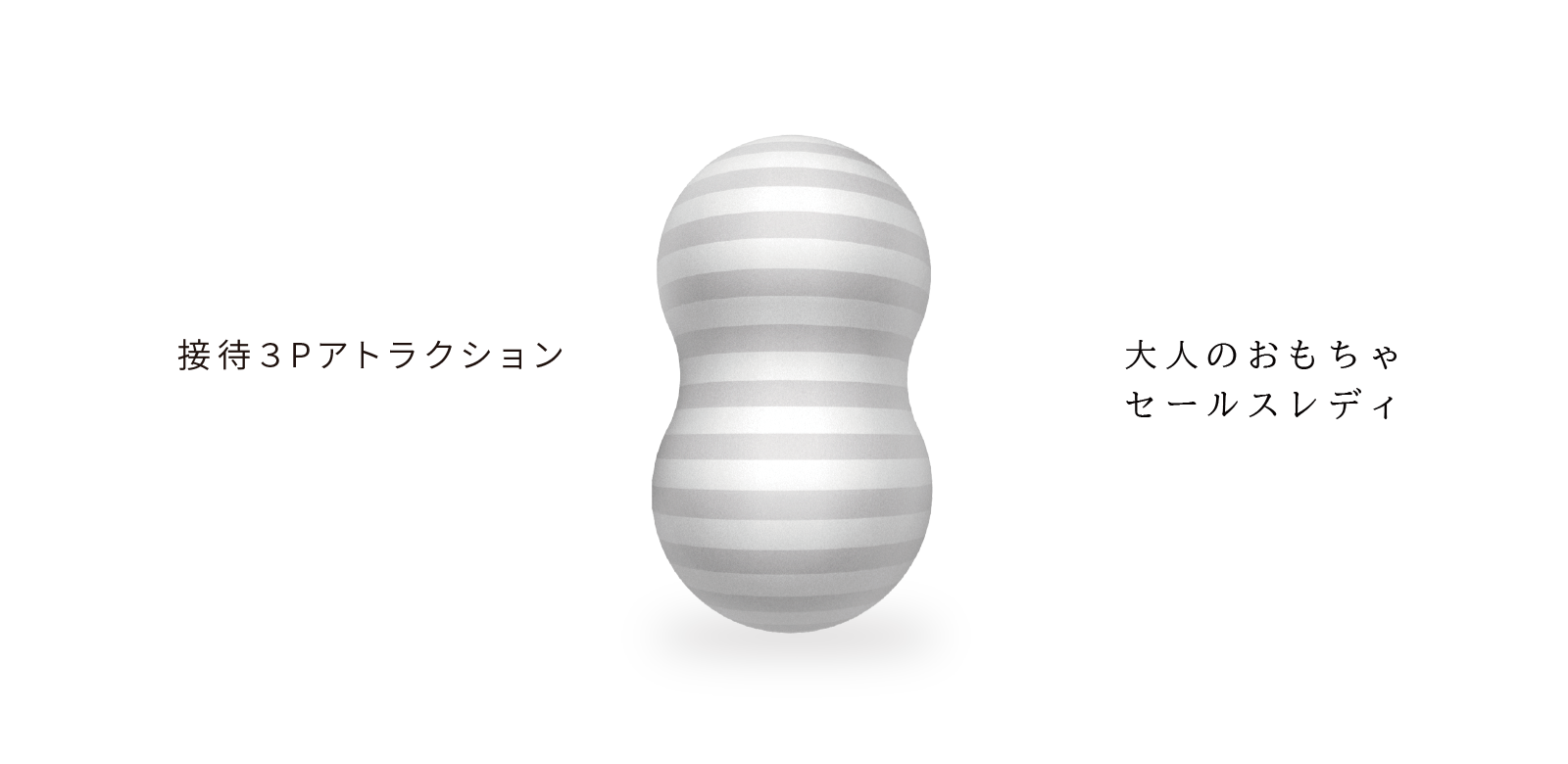


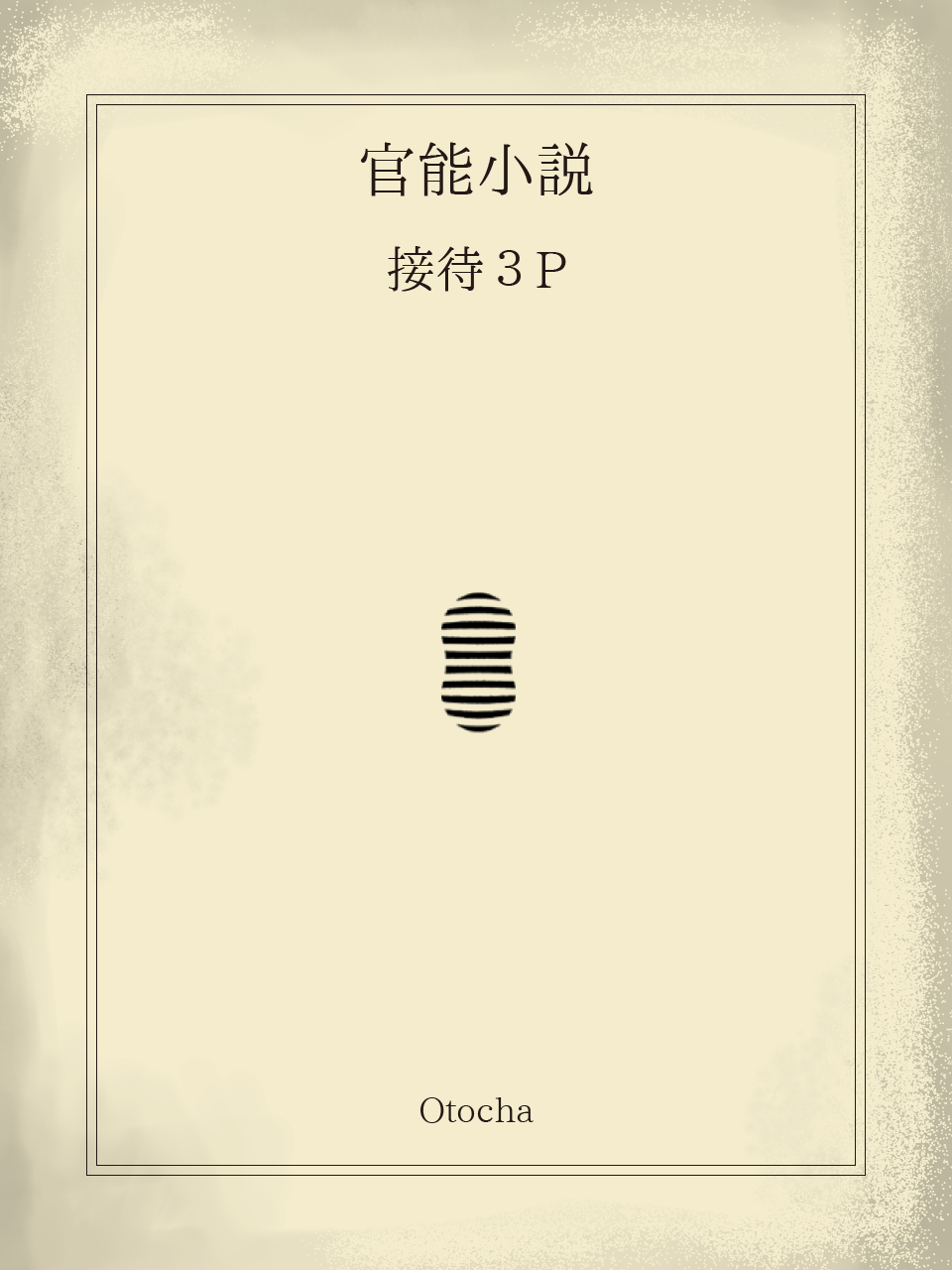


美女二人が貴方を奪い合うように
抜群のコンビネーションで
枕営業を仕掛けます。
ぜひお楽しみください。